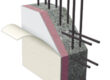傷を「美」として昇華させる金継ぎ…日本人としての心のあり方、美学とはどういうものなのか?
近年、金継ぎは単なる伝統工芸の枠を超え、サステナブルなライフスタイルの象徴として世界中から注目を集めている。なぜこれほどまでに金継ぎが世界で注目されるようになったのだろうか。そして、ビジネスやデザインの分野にまで広がった背景には、どのような要因があったのだろうか。
国や文化、宗教といった境界を越えて、多くの人々の心を動かす金継ぎ。
その魅力を探るべく、美術家であり金継ぎの活動を世界に普及させているナカムラクニオさんに話を聞きながら、世界が注目する“Kintsugi”の奥深い世界を紐解いていく。
2025年9月2日 6時0分 JBpress
金継ぎを趣味に
金継ぎです。実はこれ私の老後の趣味候補に上がっているものなんですが、まだあまり詳しく調べておりませんでした。
皆さんもご存知の通り、基本的には欠けたり割れたりした陶磁器などの器を漆で接着し、そこに金粉で装飾して修復するという技術で、日本の伝統技法とされています。
もともとプラモデルを作るのが好きだった少年ですので、そこは昔取った杵柄が活かせるのではないかと思っています。
Kintsugiのきっかけはロックバンド?
さて、ます記事にあったのは、そもそも海外で金継ぎが、Kintsugiとして広まるきっかけはあったのだろうか? ナカムラさんはこう振り返る。
「もう10年ほど前のことですが、アメリカのロックバンド『デス・キャブ・フォー・キューティー』が『Kintsugi』というタイトルのアルバムを出したんです。ロックバンドが突然“Kintsugi”という言葉を使った意外性もあって、それが大きな話題になりました。そのヒットが火付け役となり、アメリカで“Kintsugi”が流行しはじめた。それが世界へと広がるきっかけになったと思います」と書かれていました。
なんと、すでに金継ぎが海外でも人気を集めているということで、例によって「kintsugi」という日本の単語が使われるようになっているのも凄いですね。
その技法とは
次に記事にありましたので、ここで少し、金継ぎとは具体的にどのような技法なのか。改めてその基本をご紹介して頂きましょう。以下転載です。
金継ぎは、大きく分けて「接着」「補修」「仕上げ」の3つの工程に分けられる。まず「接着」は、割れた器の破片を、漆を接着剤として組み合わせていくものだ。欠けている部分には、漆に小麦粉を混ぜた麦漆(むぎうるし)や、漆と砥の粉という、石を粉末状にしたものを混ぜた錆漆(さびうるし)が用いられる。接着面はマスキングテープなどでしっかりと固定し、完全に乾くまでしばらく置かれる。
次に「補修」では、欠けや隙間を錆漆で埋め、やすりで丁寧に形を整える。仕上がりの美しさを左右する重要な工程であり、やすりではなく、とくさなどの伝統的な道具が使われることもある。
最後の「仕上げ」は、研磨した部分に漆を塗り、金粉や銀粉を蒔いて装飾する。金粉が定着するよう、真綿で軽く押さえ、最後は鯛の牙などで磨き上げて光沢を出す。こうして、壊れた器は新たな表情を得て生まれ変わるのだ。
どうでしょう。なかなか面白そうではありませんか?その手順や作業風景、時間の掛け方、さらに仕上がり表現など、そこは精神世界にも通ずる底なし沼かもしれません。
金継ぎの本質、その美学とは何なのか?
最後に記事に書かれていたのは、「金継ぎは単なる修理や修復とは全く違う行為だと感じています。ただ壊れたものを接着するということであれば、日本人は1万年前の狩猟採集の時代(縄文時代)から、漆を使って土器を修理していました。
完璧であることを求めないとき、壊れたものに美を見いだすとき、人生の価値観は変化し始めます。つまり金継ぎの本質とは、『壊れものとしての自分』を受け入れる技術なのかもしれない、と感じています」。とのこと。
このようなお話をお聞きしますと、ますますその道を探究してみたくなってしまうのは、生まれながらの器用貧乏がそうさせているように思います。
さらに著者さんは、直すという行為は、単なる修理ではない。モノの過去を再構築して、唯一無二の物体を作り出すこと。今日までお互いに生き続けることができた年月の重みを分かち合う、ささやかな祝福や祈りのようなものでもあるという。
「大切な“ちいさな宝”を、後世の人に受け継ぐために守る、尊い行為でもあるのです。金継ぎで、大切なのは傷に対して“味がある”と感じることではないでしょうか。我々日本人は、古びて、傷があった方が“かっこいい”と考えることができます。“傷”を“味”と呼ぶ美意識と“無用の美”を愛でる感性こそ、金継ぎの美学です。と書かれていました。
近代の日本人では、家電製品や車を始めとする工業生産に目が慣らされているためか、ランダムな模様の左官仕上げ、コンクリート打ち放しなどをご理解頂けないケースもあるようです。
如何だったでしょうか。記事にありましたように、日本の侘び寂び、粋、または美意識を追求してみたくなりましたでしょうか。是非ご一緒にチャレンジしてみましょう。