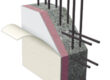4年住んでわかった!「ゴミ箱どこに置く?」も解決。「家づくりで必ず確保したい収納場所」5選
住んでからの後悔を少なくするためには、間取りを考えるときの「ひとがんばり」が重要です。4年前にハウスメーカーで家を建てたライターは、ゴミの保管場所、プリンターや防災用品などの収納スペースについて、「前の住まいでの反省」を徹底的に活かして、間取りに反映させたことで、今もそれらの収納に困ることはない、といいます。
2025年7月13日 21時4分 ESSE-online
住まいの不便さ
人の日々の暮らしでは、おおよそルーチンというか慣れというか、潜在意識にお任せで行動していることも多いと思います。
そんな中で違和感なく続けられていることは、それほど問題とはならず順調に暮らしを続けられているということかもしれません。
しかし、どうもこのひと手間が面倒に感じるとか、家族の中でしっくりこない人がいるとか、なぜかいつも目につくところに置いてあるとか、そんなことがあったら何かのヒントではないでしょうか。
今日の記事では、記事のライターが「やってよかった」と感じている家づくりのポイントについて語ります。4年住んだ今、やはり計画してよかったと思う「ゴミ一時保管スペース」「ストック置き場」「プリンターとシュレッダー」「防災用品置き場」「充電スペース」について、レポートします。ということです。
ゴミ箱置き場
まずはゴミ箱の置き場所、皆さんはどうしていますか? キッチンやカップボードに配置する方も多いと思います。わが家も最初はそのつもりでした。
でも、実際のわが家のゴミの量を考えると「このスペースではたりないかも…?」と不安に。そこで、どれくらいの大きさのゴミ箱が何個あればたりるのかを考えるために、ゴミの種類ごとの量を把握することから始めました。
引っ越し先の分別方法は、燃えるゴミや燃えないゴミ、そのほかリサイクル用分別回収が7種類ということです。
このなかで、収集日のたびに必ず捨てる&量が多いのは「燃えるゴミ」と「容器包装プラスチック」。この2つには、大きめの専用ゴミ箱を用意しました。
やはりモデルルームにあるような標準的なゴミ箱スペースではたりないことが判明。アクセスのよいキッチンやカップボードに広いスペースを割くのはもったいないと感じ、キッチン横のパントリーにゴミ箱スペースを確保することにしました。結果、使いやすく、家族みんなが迷わずゴミを分別できる環境が整いました。ということです。
自分たち家族の生活を見直すというか、じっくりと観察することがまずは大切で、家族の人数や年齢などによってもゴミの量って全然違いますからね。我が家の現実を一度は正確に把握することから始めるといいと思います。
ストック置き場
ストック収納は「使う場所の近く」がベスト
次はストック収納です。食料品だけではなく、ボックスティッシュや掃除用具などのストック品は、意外とたくさんありますよね。面倒くさがりの私は、なくなったらすぐに補充しないと困る消耗品は、必ずストックしています。とのこと。
ストックする場所は、すぐ使えるように「使う場所の近く」にしました。
プリンター等
毎日使う電子機器はストレスフリーな配置で
前のマンションでは、リビングに天井までの高さの壁面収納を設置していて、そこにプリンターを入れていました。目線の高さに合うので、一度立たないといけない。さらに扉をあける必要があり、プリンター用紙の予備は離れた書斎にあるなど、面倒くさがりの私にはとても使いにくかったです。
その経験から、今の家では「座ったままスイッチが押せる」「扉をつけなくても隠せる」ことを重視して、私の机の左側にスペースを確保しました。
なんでも隠そうとしてしまうと、これが意外と面倒になってしまうということもありますね。実は使用頻度が高く、毎日、一日に数回という場合は扉が無い方が便利かもしれませんので、このあたりも生活を観察する必要がありますね。
防災用品置き場
記事の著者さん宅では地震に強い家を選びました。ということで、そのためある程度の強い地震が来ても、自宅を一時避難場所とすることを想定していますということでした。
ただ、万が一避難所への移動が必要になった場合に備えて、最低限の荷物をリュックに入れて準備しています。いざというときにすぐ取り出せるよう、玄関クロークに配置。ここであれば、わざわざ別の場所まで非常用リュックを取りに行く必要がありません。と書かれていました。
充電スペース
最後は「充電スペース」について書かれていました。わが家は、子どもが3人。それぞれスマホを持っています。でも部屋で充電できるとエンドレスで使ってしまいます。また、家のあちこちで充電すると充電ケーブルが散らかりっぱなしになってしまいます。
そのため、1階にスマホやワイヤレスイヤホンなどを充電するための充電スペースをつくりました。家族がよく集うリビング・ダイニングから近く、しかも目立たない場所なので、来客時にも生活感を感じさせにくいと思いました。
コンセントも配置し、子ども3人と私のスマホを立てたまま充電できるようにしました。また、ここに子どものスマホを並べる場所を確保することで、寝る前に部屋にスマホを持っていかないという約束が守られているか、パッとわかるようになっており、使いすぎを防いでいます。とのこと。
このあたりは子育て世代のご家族には参考になるかもしれませんね。一方で中高年以降の場合はどうしてもベッドサイドという方も多いのではないでしょうか。そんな場合は充電方法を検討の上必要な場所にコンセントの設置が必要になります。
生活スタイルは人それぞれですので、全ての人が同じ暮らし方をしているわけではありません。一般的に合わせるところも必要かもしれませんが、目的を自分たち家族がストレスなく暮らせることだとすれば、その解決方法を考えるのが設計者の仕事です。是非ご一緒に住まいづくりのお手伝いをさせてください。