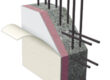「ブルーカラー・ビリオネア」を生んだ米国の建設業界…若者が殺到、熟練工の平均年収は1200万円!
アメリカではAI(人工知能)の発展で事務職の需要が大幅に低下、代わって建設業など肉体労働に若者が殺到している──そんなニュースが話題だ。ブルーカラー・ビリオネア(肉体労働の億万長者)という造語も生まれたらしい。
2025年11月13日 15時5分 日刊ゲンダイDIGITAL
記事を読み解く
これはちょっと羨ましい記事です。
熟練工の職人さんの地位と収入が保障されるようになれば、若者の挑戦者が増えるでしょうし、憧れの職業としても一定の人気をキープ出来るようになって、全体の技術もより発展することでしょう。
記事によれば、全米電気工事士組合の統計によると、組合に所属する熟練工の平均年収は8万ドル(約1200万円)を超える。日本の建設業平均年収510万円と比べれば、倍以上の開きだ。全米の全職種の平均よりも高い。と書かれていました。
いやいや、ここは単純に比較してはいけないように思います。ここ数年の日本の弱体化によって、ビックマック指数の格差は広がるばかりで、それだけ物価の基準が違いますからね。
ちなみに最新の情報によれば、アメリカのビックマックは日本円にして874円、日本は480円ですので、1.8倍となっています。参考に世界で一番高いのはスイスだそうで、1207円相当だそうです。
AIの影響ではない
記事では、この現象についてアメリカの事情に詳しい経営者が語られていました。
「この高給化はAIよりも、2021年から始まったインフラ投資雇用法の影響が大きい。コロナ禍における財政出動で連邦政府により、総額1兆ドル規模の公共工事が動き出した。建築需要は急増した一方で、もともと建設業はベビーブーマー世代の大量退職が2010年代から続き、若年層の入職率は低迷していた。需給バランスがひずみになり、賃金が上昇したに過ぎない」とのこと。
これはつまり、AIではなく政府出動や社会構造の変化が高給につながったということのようです。
日本の場合は
同様に日本の場合はどうか。
記事にあったのは、アメリカ同様に日本でも、建設業界の人手不足は慢性化してはいる。だが、アメリカで起きたブルーカラーの高給化が日本にそのまま当てはまるかは別の話だということ。
「アメリカの建設業では、職種別組合が強い交渉力を持つ。電気工、配管工、大工──それぞれの組合が賃金基準を設定しており、他の業種からうらやましがられるほどの医療保険や年金、傷病手当もある。昨今の人手不足を受けて、新人育成も手厚い。訓練期間中にも給料が支払われ、数年かけて体系的に技能を習得する仕組みがある。若者人気はこうした実利があるからだ」とも書かれていました。
価値ある技術と商習慣
そうなんです。そんなシステムを日本でも実現しませんと、本当に日本のものづくりが出来なくなってしまう日が来てしまうように思います。
日本人は人の持っている技術や芸術性に対してあまりにも評価が低いですし、そこにも安さが一番という価値観が広まってしまっているのではないでしょうか。
記事では、一方日本の不動産・住宅市場の現場では、高度経済成長期から続く、多重下請けの慣行が今も残っている。元請けから、現場で実際に働く職人へと資金が流れる過程で、何層もの中間マージンが差し引かれるのが常識だ。
現場の声を聞けば「仕事はあるが儲からない」という嘆きがあふれる。そもそも日本の建設業界には、技術を高く売る仕組みが存在しないのである。とも書かれていました。
適正な価格としくみづくり
そして、アメリカで起きているブルーカラーの高給化を「AI時代の勝ち組」として語るのは、確かに分かりやすい。だが、それには長年の労働者の努力とマーケットの力学があるようだ。
日本で建設現場の職人を救うのはAIではなく、技術を育て、それを正当に評価する仕組みを整えることだ。「ブルーカラー革命の前に、まずブラック構造を何とかして欲しい」が現場の本音だろう。とありました。
もののお値段にはある程度相場観というものも存在しますが、一方で同じ素材同じ機能でも大きな価格差のあるものもあります。そこにどのような価値が存在するのか、求める人によって様々な価値観があると思いますが、そこのすり合わせや共有が住まいづくりには大切だと思います。
弊社では、自社の職人さんやスタッフの持つ知識と技術の安売りはしません。適正な価格にどうかご理解を賜りますようお願い申し上げます。