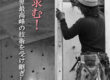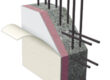家じゅうにフック、「壁かけ収納」に変えて床置きがなくなった。コツは「暮らしの動線上」につくること
床にバッグや服を置いてしまう…。そんな自分を「片付け下手」と感じていませんか? じつは、床置きが続くのは意志の弱さではなく、“脳の仕組み”が原因なんです。暮らしの動線上に「かけるだけで片付く」仕組みをつくることで、無理なく整う部屋に変わります。
2025年11月20日 20時0分 ESSE-online
我が家でも実践中
これですね、実は我が家でも10年前から導入していまして、まずは玄関にあるフックに犬のリードなどがかけてあったり、リビング前の廊下にはアウターをかけるフック、個室にはデニム用フックなどを設置しています。
当時は毎日使うものや、花粉の付着している衣類をクローゼットにしまいたくない、などの理由からフックの設置を考えました。
脳のしくみです
床置きが片付かないのは、脳が“未完了”と感じているから
記事によれば、人の脳は、視界に入ったものを常に処理しようと働きます。つまり、床にものがあると「まだ片付いていない」と無意識に感じ、それがストレスや疲労感を生む原因になります。
一方で、フックなどに「かける」行為は、脳にとっては“完了のサイン”。わずかな動作で達成感が得られるため、片付けを続けやすくなるのです。
床置きの原因は意志の弱さではなく、“仕組みの位置”が合っていないこと。動線上にかける仕組みを置くことで、自然と整う空間が生まれます。と書かれていました。
そんな脳科学的な理由があったとはビックリですが、確かにフックにかけただけで片付けた気になるという感覚はわかるような気がします。
動線上に配置
著者さんの家では、“動線の途中で完結できる片づけ”を意識して壁かけを設置しています。
片づけ下手の原因は「意志の弱さ」ではなく、“動線に合っていない仕組み”にある。だからこそ、かけるだけで完了する仕組みを“動線上”に置くのがポイントです。とのこと。
著者さんの家では下記の場所に設置されているそうです。
1:洗面所に行く廊下のフックで“帰宅スイッチ”を入れる
2:キッチン横のフックで“とりあえず置き”をやめる
3:ダイニング入り口のペグボードで“定位置を見える化”
4:ダイニング正面のフックで“忘れものゼロ”に
5:洗濯室のフックは“家族みんなの帰宅動線”のなかに
さらに工夫されている点としては、それぞれの身長に合わせてフックの高さを変えているため、子どもも“自分でかけられる”感覚をもちやすく、帰宅後の流れの中で自然と片付けが完結します。だそうです。
散らからない家をつくる
また、「とりあえず置く」をなくすポイントは、家族1人1人の動線と行動パターンを想定して“高さ”まで整えること。無理なく続く仕組みづくりが、散らかりにくい家をつくります。と書かれていました。
もちろん最終的にはクローゼットなどの各種収納に収められるものもあると思いますが、毎日の生活を無理なく気持ちよくすることを目的にするなら、このフックを有効に使うのもいいアイデアではないでしょうか。
やり過ぎは如何なものかと思いますが、収納の補助として、または一つの形としてご興味のある方は是非設計士にご相談ください。