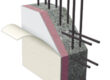建築士が語る「住み心地のよい家」の3つのポイント
家にいることに幸せを感じたり、住まいのおかげで日々が充実するように、住み心地のよい家は人生を豊かにしてくれる。でも、「好みの家」について言葉で説明するのは案外むずかしい。どうすれば、自分らしく生きられる家、居心地のよい住まいをつくることができるのか。
2024年7月24日 18時0分 新刊JPニュース
住まいづくりのヒント
住まいづくりをお考えの方には、タイムリーでキャッチーな記事だったかもしれません。
今日の記事では、40代からの住まいリセット術などの著書があるという新築・リフォーム実績130件以上の一級建築士さんが、自分らしく住まう家をつくるための自分でできる住まいリセットの方法を紹介されていました。
二つの条件
記事にあったのは、住み心地のよい家の条件は大きく分けて2つある。1つ目は機能性。使い勝手がいい、片付いている家だ。2つ目は、精神性。住む人の目に映る心地よさ、つまりインテリア的要素だ。雰囲気があって、のんびりくつろげる家は、心に充足感をもたらしてくれる。インテリアが自分の趣味・嗜好に合わせてコーディネートされているか否かで、住まいへの満足度は大きく変わってくる。ということ。
確かに機能性と意匠性がその家の満足度を上げるのに、大切なことに違いありません。が、ここは全ての人に共通する基準があるかというと、そうではなく人それぞれの基準を持っていたりしますので、誰にとっての最善かということになるかもしれません。
三つのポイント
次に、機能性と精神性の充実した住み心地よい家を実現させるための3つのポイントが「短い動線」「適材適所の収納」「自分らしいインテリア」だ。これらの3つは、どれかひとつが欠けても住み心地のよい家にはならない。とも書かれていました。
動線を調整し、間取りのねじれをただすと、生活の中で無駄な動きが減り、時間の効率がよくなるというメリットがある。そして、動線上の最適な場所に収納を設けることで、片付けを意識しなくても、自然に片付き、散らからなくなるというもう一つのメリットが生まれる。
動線と収納が整うと、雑多なものに視線を奪われることがないため、インテリア全体を上手にまとめることができるようになる。インテリア上手になるには、まず自分の好みやスタイルや基本的なことを理解すること。最終的には自分自身が心地いいと思うインテリアを自由につくっていくのがよい。とのことです。
模範解答
まさに建築士として模範的な解答と言える内容だと思います。私たち建築士も実は細分化や専門化が進んでいて、同じ建築士と言えども住宅が専門の人がいれば、商業施設や工場が専門という人もいますし、構造が専門だったり、設備が専門という建築士もいるんですね。
私の場合は一級建築士の資格を取得して以降、35年間住居系をメインに事務所や医療機関などの設計に携わらせて頂きましたので、やはりそこに暮らす人の生活を考えてきたように思います。
記事の著者も書かれていましたが、家づくりの真の目的は、住む人が幸せになることだと思いますし、住まいを考えることは、これから十年後、二十年後、どんな家でどんなふうに暮らしていきたいのかを考え、自分を見つめ直すことにもつながるでしょう。
ライフスタイルを実現し、自分と家族が居心地のよい家づくりが出来れば、より良い時間を過ごすことが出来ますので、それを定期的に見直したり修正しながら育てた家が、きっといい家になるのかもしれません。
あなたの住まいづくりのお手伝いを、是非私たちにさせてください。