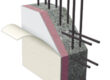能登半島地震から1年…専門家がアドバイスする「災害時のスマホ活用法」 4つの事前準備も忘れずに
2024年の元旦に発生した能登半島地震から約1年。地震情報の入手にスマホややテレビはどう活用されたのか。
NTTドコモのモバイル社会研究所(東京都千代田区)が2024年12月11日に発表した調査「【防災】能登半島地震 最初に接した手段は震源に近いとインターネット経由が多い」によると、意外なことに震源地に近いほど、第一報入手にスマホを活用する割合が高くなる。
いったいなぜか。災害時にスマホをどう活用したらよいか。調査担当者に聞いた。
2024年12月25日 18時6分 J-CASTニュース
進まない復興
年々時間が経つのが早くなるのが人生だと思いますが、能登半島地震からもうすぐ1年となると、被災地の復興が進んでいないことに苛立ちを覚えます。
相変わらず行政の指導力や防災対策は進んでいませんし、国民の皆さんも災害に対する意識と対策をお忘れの方が多いように思います。
情報収集について
いつもお伝えしていますように、災害は時と場所を選びません。この機会に今すぐ出来る対策を行なってください。
今日の記事にあったのは、モバイル社会研究所の調査(2024年11月)で、全国の15歳~79歳男女1万355人を対象としたものだそうです。
まず、能登半島地震発生の情報を最初にどんな手段で知ったかを聞くと、3人に2人がテレビと答えた。発生日時が元旦だったため在宅していた人が多かったことが影響していそうだ。と言うこと。
一方で、インターネットを通じて情報を得た人は26.5%。インターネット経由の内訳は「SNS」「サイト閲覧」「スマホの防災系アプリ」「エリアメール・緊急速報メール」の順だったそうです。
テレビよりネット
そんな中で興味深いのは、地域別(回答者の住所)にどんな手段で最初に地震の情報を知ったかを聞いた結果で、震源に近いほどインターネット経由で知った割合が高く、震源から遠くなるほど、テレビの割合が高くなる。震源地の石川県は全国で唯一インターネット経由(44%)がテレビ(41%)を上回った。とありました。
次に年代別にインターネット経由とテレビの割合を調べると、20代は両者が拮抗。年代が上がるにつれテレビの割合が増え、70代では8割以上がテレビで初めて能登半島地震を知ったということでした。
やはり一般的に高齢者ほどテレビを信頼しているようですが、この先は徐々にネット人口が増えるのではないでしょうか。
防災ガイドもチェック
さらに最初に得た情報以外にどのような方法で次々と流れる情報を得たかを調べた結果、最も多かったのはサイトの閲覧。多くの人は最初にテレビを通じて地震の情報を知り、その後インターネットで詳しい内容を調べていた。とありました。
モバイル社会研究所では、災害時に役立つ調査結果を多く掲載した「データで見る防災ガイド」を公開している。と言うことで、下記リンクより一度ご覧頂けますようお願い申し上げます。
4つの事前準備を
研究所の方によれば、当ガイドにも記載しましたが、「災害時の連絡方法をご家族で確認する」「安否確認ツールの利用方法の確認」「防災系アプリのインストール」「スマホの節電対策」の4つを平時に実施・確認することをお願いしたいと思います。と書かれていました。
これら「災害時のスマホ活用法」 4つの事前準備も忘れずに行なっておくことが大切ですね。
公衆電話を使えない人も
最後に、通信設備が大混乱して、スマホが使えなくなった時の対策も合わせてお願いしたいです。特に若年層の方は公衆電話の使い方を練習しておきましょう。また、スマホに内蔵しているご家族の電話番号の控えを取っておくことも重要です。ともありました。
公衆電話の使い方って、そうなんですね、すでに生まれた時からスマホがある世代が世の中に出てきていますので、昭和世代は一々常識を疑ってみることが大切ですし、その上でしっかりと災害対策を行なってください。
住まいはRC住宅をご検討くださいね。