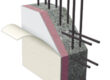地価上昇率上位は中央、港、目黒区 東京23区、前年を上回る伸び幅
東京都は18日、土地取引の指標となる公示地価(1月1日時点)を公表した。
前年と比較できる都内2542地点のうち、2483地点で価格が上昇。平均変動率は前年比7・3%の上昇で4年連続のプラスとなり、上昇幅も前年を上回った。都心部を中心としたマンション需要は高いままで、インバウンド(訪日外国人客)の増加で商業地での上昇傾向も続いている。
2025年3月18日 16時50分 朝日新聞
公示地価
毎年恒例の公示地価が発表されました。
一応おさらいしておきますと、公示地価とは、地価公示法に基づき国土交通省の土地鑑定委員会が標準地を選び、毎年1月1日現在の宅地標準地について国土交通省が公表する正常価格のことで、民間取引の指標とされ、公共収用の基準となるものです。
土地の価格にはこの他にも課税評価のための「路線価」と「固定資産税評価額」がありますが、もちろん実際の市場における売買価格は別にあります。
便利な「不動産情報ライブラリ」というHPでは、不動産の取引価格、地価公示等の価格情報や防災情報、都市計画情報、周辺施設情報等、不動産に関する情報をご覧になることができる国土交通省のWEBサイトです。下記よりご覧ください。
23区の上昇率
さて、記事によれば、上昇率は23区全域で9・6%(前年6・0%)、多摩地区は3・8%(同3・0%)だった。ということです。
項目別にみると、住宅地の上昇率は都内全域で5・7%(同4・1%)。23区は7・9%(同5・4%)で、多摩地区は3・4%(同2・7%)だった。
さらに23区の上昇率は中央区の13・9%(同7・5%)が最も高く、港区12・7%(同7・2%)、目黒区12・5%(同7・3%)と続き、いずれも前年を上回る上昇となった。タワーマンションの建設が進む地域や、都心部へのアクセスがいい区を中心に幅広く地価が上昇している。ということ。
足立区や北区が
他の記事でも取り上げられていたのが、上昇率で上位につけた足立区の綾瀬駅周辺だということ。もちろんそれなりに要因があってのことですが、綾瀬以外にも、都心の周辺地域で上昇が目立っていたようです。
23区の住宅地の地価上昇率ランキングでは、北区赤羽1丁目が4位、同区滝野川5丁目が9位に入るなど、周辺部での需要が高まる傾向が続いているとも書かれていました。なんともローカルなお話しになってしまいますが、ここがトップ10に入るなんて誰も想像していなかったと思います。
商業地では
商業地では、都内全域の上昇率は10・4%と、前年の6・3%から大幅に上がり、リーマン・ショックがあった2008年以来となる2桁の伸びとなったそうです。
こちらも23区では、中野区の16・3%(同8・2%)がトップで、続いて杉並区が15・1%(同8・0%)、台東区が14・8%(同9・1%)だったということ。
今年の傾向
今年の傾向について都財務局によると、浅草や上野といった23区内の商業地では、インバウンド需要の好調に加えて住宅としての需要も広がり、低層階は店舗、上層階はマンションが立ち並ぶ地域で上昇率が高かった。
多摩地区は、再開発が進むJR中央線や京王線の駅前周辺で店舗需要が回復し、マンション需要との競合で上昇したとみている。
都心部の住宅価格の高止まりで、外縁部に人が流れている。中でも電車通勤の利便性が高く、これまであまり注目されていなかったエリアが『割安』と評価されて地価が上昇している傾向があると指摘されていました。
すでにここ数年、想像を超えた高騰が続いていましたので、都心部ではとても一般国民が手を出せる価格ではなくなっています。となると現実的な価格感としては他県に接する区部あたりなら、まだまだリーズナブルと言えると思います。
こと家づくりを考えれば、土地の価格と建物の価格バランスはとても重要で、土地を先行してしまうと残念な結果になってしまう可能性が高まってしまいます。建築費も高騰が続く中では土地代を極力抑える努力も必要かもしれません。
東京23区で家を建てるなら、是非お気軽にRCdesignまでご相談ください。