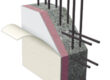100年統計で判明…「長寿1位」へ大躍進の滋賀県民が「短命県」転落の沖縄県民の半分しか着用しない「夏アイテム」
現在は長寿の都道府県でも昔はそうではなく、短命であったケースも多い。それはどんな地域なのか。戦前からの約100年間の統計を分析した本川裕さんは「滋賀の男性はバブル期以降、女性は2000年以降に躍進を続け、2020年に男性は長寿1位、女性は2位の地位を手に入れた。かつて1位だった沖縄がすっかり凋落した理由があるように、長寿化・短命化するのには社会的背景がある」という――。
2025年4月9日 10時15分 プレジデントオンライン
寿命の地域格差
これは本当に意外な結果ではないでしょうか。恐らく多くの日本人は南の方にお住まいの方が長生きで、寒い地域ほど短命ではないかと思っているのではないでしょうか。
確かにそういう時代も有りましたが、今はそんな地域性だけではなく、医療格差などの要因もあるようですので、どこに暮らすかによっても寿命が変わってくるようになったみたいです。
まず記事にあったのは、先日この30年間に47都道府県で平均寿命の最長と最短の差が男性で2.3歳、女性で2.9歳拡大したとの慶応義塾大などのチームによる分析結果を報じられ、話題となった。どの地域が長生きか、またどの地域が短命かという点に関する関心は依然高いと考えらえる。とありました。
滋賀県って・・・
その結果が、直近の最も長寿な県は滋賀であり、男性では2015年、2020年と連続2回で第1位となり、女性は2015年の4位から2020年には2位に躍進している。滋賀は、かつては寿命の長い県ではなかったが、男性はバブル期以降、女性は2000年以降躍進を続け、現在の最長寿県の地位を手に入れている。ということです。
滋賀県って、大変失礼ながらほとんど存じ上げることがございません。もちろん琵琶湖があったり、以前に家電メーカーの工場見学にお伺いしたことがあるくらいで、なかなか身近に滋賀県出身という人もいませんので、ほとんど情報が届いていません。
そんな滋賀県が長寿な県になったというのは、どのような要因があったのでしょうか。記事にあった長寿命の地域について見てみましょう。
その要因は
2020年の統計データ公表後、長寿県として滋賀の取り組みがテレビでも取り上げられ、喫煙率、飲酒率の低さや運動がさかんといった点が指摘された。とありました。
実は、滋賀のほか、福井、富山、石川といった北陸地域、あるいは島根で以前の短寿命から長寿命への似たような躍進が見られる。富山については推移を特記されていて、これは気候風土上の不利性が栄養改善などで好転したからだと考えられるということでした。
サングラスの影響は
次の調査結果が興味深かったのですが、眼鏡屋さんのJINS調べの「メガネ白書2022」によるとサングラスを使用している人の割合が最も低いのは滋賀であり、鳥取、富山がこれに続いていた。ということなんです。
つまり、こうした地域は日射しが弱いのでサングラスの必要がないのである(逆に割合が最も高かったのは沖縄で長崎がこれに続いていた)。
記事の著者さんによれば、祖父が富山県の氷見出身であるが、かつて氷見は「くる病」で有名だった。くる病は紫外線(日光)不足や栄養不足によるビタミンDの代謝障害によってカルシウム、リンの吸収が進まないために起こる病気であったが、栄養分の中でもビタミンは外部補給が容易なため途上国においてもこうした疾患は最近見られなくなったそうです。
つまり気候風土上、短命だった地域は、それを克服するため、栄養対策など近代的な健康対策を進めるとともに、県民も健康によいことをしようという前向きな生活態度を守ることとなり、長い間にそれが功を奏して、滋賀や日本海側の短寿命地域は今や長寿命地域へと変貌したものと考えられる。と書かれていました。
短命になったのは
一方で、長寿地域として躍進した滋賀や北陸地域と正反対なのが、サングラス着用率の高い沖縄や長崎で、沖縄や長崎は戦前(長崎は戦後しばらくも)、長寿命地域として目立っていたが、近年は、短命地域化しているということ。
記事によれば、これは滋賀や北陸地方とは反対に、気候風土に恵まれているという有利性が近代的な生活環境の中では十分に発揮できなくなってきたからではないだろうか。厳しい目でみると、温暖な気候が油断を生み、野放図な生活態度を許しているから短命地域化している可能性があろう。ということでした。
ちなみに沖縄の平均寿命は2020年段階では男では43位、女では16位でした。
相変わらずなところも
さらに残念なのは青森県で、戦前から男女ともに寿命ランキングが低く、男性は1975年以降、女性は少し遅れて2000年以降、最下位を続けている点が目立っている。ということ。
記事によれば、青森県民の短命の理由として指摘されるのは、①喫煙率の高さ、②多量飲酒者の多さ、③肥満者の多さという3つの生活習慣に加え、④塩分摂取量の多さ、⑤運動不足、⑥医師の少なさ、⑦健診率の低さ、⑧病院受診の遅れ(病気が深刻になるまで病院に行かない)も関係しているとされる。さらにその背景として、①気候(寒さ、雪)、②経済力の弱さ、③青森県独特の文化・気質などがあるとされる。ということです。
取り組むことが大事
人間の目も年齢と共に変化するようで、徐々に眩しさを感じるようになるようですし、紫外線の吸収は目からとも聞いたことがありますので、サングラスが手放せないという方もいらっしゃると思います。
今日の記事では、サングラスが全てではありませんが、健康維持に関しては終わり無く、青森県の皆さんを反面教師にして淡々と継続することが大事だということではないでしょうか。
さらにRC住宅がそんな健康をサポート出来れば良いと思います。